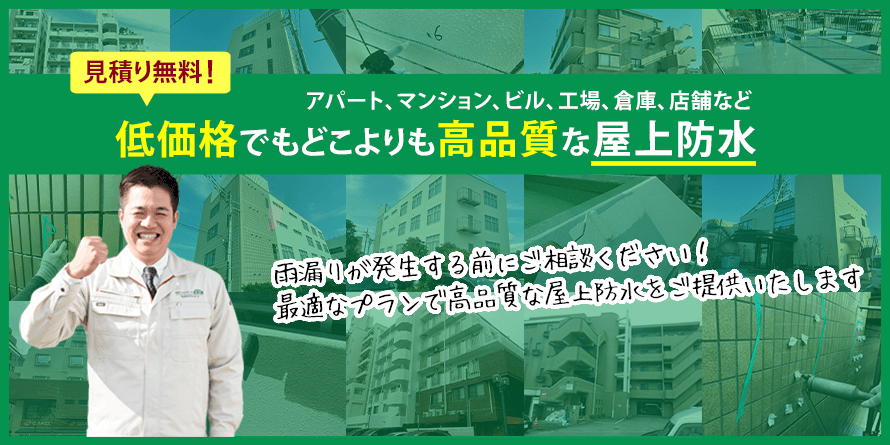
防水工事とは、屋上やベランダ・バルコニーの床面に防水材を施工して層を作る工事を指し、最も重要な目的は雨水の浸入を防ぐことです。
屋上の床面はほぼ水平であるため、雨が滞留しやすい場所となります。適切に防水工事が施されていないと、滞留した雨水が下地のコンクリートに染み込んでいき、雨漏りに発展してしまいます。
防水工事を行って床面をしっかりと保護し、正しく雨水が排水されるように施すことが重要です。
雨水が屋上の床面に染み込んでいくと、やがて建物全体に水分が回り、雨漏りだけでなく鉄部のサビや木材の腐朽など、建物を支える建材の腐食に繋がります。
さらに、雨水の浸入はシロアリやカビの発生、耐震性の低下などのトラブルを招く恐れもあり、建物寿命に大きな影響を及ぼす原因となってしまいます。
雨漏りは建物の資産価値を下げる大きな要因となります。建物寿命を延ばし、資産価値や居住者の満足度を高く維持する為にも、防水工事を実施して雨漏りを未然に防ぐことが大切です。
また、雨水が室内や共用部分まで漏れ出してしまうと、入居者の私物や家財が濡れてトラブルになったり、足を滑らせてケガをするなどの事故に繋がる恐れもあります。そのため、定期的なメンテナンスが重要となります。
防水工事を行う時期は、防水層の種類や周囲の環境などにより異なりますが、一般的に10~15年ごとに実施するのが望ましいです。
ただし、劣化状況によっては早めにメンテナンスが必要になる場合もあるため、定期的に定期的に点検を行い、劣化がみられる際は専門業者に相談するようにしましょう。
次のような劣化症状を見つけた時は、防水のメンテナンスが必要です。
屋上の防水面は、「下地→防水層→トップコート」の3層構造になっています。
防水機能を担っているのは防水層で、表面に施されたトップコートには防水層を紫外線から守る役割があります。
トップコートのひび割れであれば、すぐに大きな問題に発展する可能性は低いですが、防水層にひび割れが起きている場合は早めの対処が必要です。ひび割れを放置していると、亀裂部分から雨水が浸入して雨漏りに繋がってしまいます。
防水層が膨れていたり、剥がれ・破れがみられる際は早急なメンテナンスが必要です。
膨れは、防水層内部の水分が蒸発し、外に出ようと内部から防水層を押し出すことが原因で発生します。そのため、膨れが起きているということは、既に防水層内部に水分が浸入している証拠と言えます。
内部に水分が浸入する原因はいくつかありますが、施工時に高圧洗浄の水が残ったまま作業を進めていたり、劣化箇所から雨水が入り込んだというケースが挙げられます。
そして、膨れを放置していると、やがて剥がれや破れを引き起こします。剥がれ・破れが起きている状態では、防水層による防水機能が発揮できないため、雨水が染み込んでしまったり、下地の劣化を進行させる原因となってしまいます。
床面に水溜りができている場合も要注意です。
通常は、雨水が排水口に向かって流れて行くように勾配が付けられていますが、勾配不足が起きると雨水が正しく流れて行かずに、排水できずに溜まった水が滞留してしまいます。
勾配不足が起きる原因も様々ですが、施工不良や建物の劣化による歪み、地盤沈下などが考えられます。
水溜りを放っておくと、水分によって防水層の劣化を早めてしまい、さらに溜まった水分が劣化箇所から一気に内部へ浸入する恐れがあるため、早めに勾配を調整し直す工事を行うことが大切です。
防水メンテナンスの方法は、大きく分けてトップコートの塗装と防水層の改修工事の2通りあります。
防水層の表面には、防水層を紫外線から保護する為にトップコートが塗装されています。トップコートも経年劣化によって機能が低下したり、ひび割れが発生するため、5年に1度を目安に塗り替えを実施するのが理想的です。
トップコートの劣化を放置していると防水層を保護できなくなり、防水層の劣化を進行させてしまいます。トップコートを定期的に塗り替えることで、防水層の寿命も延ばすことに繋がります。
トップコート塗装の費用は、防水層の種類によっても異なりますが、㎡あたり2,000円~3,000円が相場です。
防水のひび割れ、膨れ、剥がれが起きている場合は、防水層そのものを作り直す工事を行います。
工法は大きく分けて、ウレタン防水、FRP防水、シート防水、アスファルト防水の4種類あり、それぞれ特徴や耐用年数などが異なります。
工法を決める際は、施工場所の形状や面積、使用用途、既存の防水層の種類などを考慮して選びます。
防水層の改修工事にかかる費用は、工法や下地の状態などによって異なります。工法については次項で詳しくご説明いたします。
施工単価:4,000~7,000円/㎡
耐用年数:約10年~12年
ウレタン防水とは、液状のウレタン樹脂を塗り重ねて防水層を成形する工法です。
液状の防水材を使用するので、複雑な形状でも施工がしやすい特徴があります。また、継ぎ目のないシームレスな仕上がりになるため、雨水の浸入リスクを最小限に抑えることが可能です。
さらに、ウレタン防水の場合は、既存の防水層の上から重ね塗りもできるため、メンテナンスも比較的しやすいメリットがあります。
ただし、職人の技術力によって仕上がりが左右されるため、注意が必要です。ウレタン樹脂を均一に塗布しなければならず、施工に不備があると本来の機能を発揮できなくなります。
施工単価:約5,000~8,000円/㎡
耐用年数:約8年~10年
FRP防水とは、ガラス繊維とポリエステル樹脂を組み合わせて防水層を成形していく工法です。
ウレタン防水と同じく液状の防水材なので、複雑な形状の場所でも施工しやすく、継ぎ目のない仕上がりになり、雨水の浸入リスクを抑えることができます。
また、軽量でありながら衝撃にも強い特徴も持っているため、歩行頻度の多いベランダ・バルコニーに適しています。
デメリットは、強固な仕上がりになるため伸縮性に劣る点です。古い建物で下地が歪みやすい場合や、木造などの収縮性のある住宅に施工をすると、防水層が建物の動きについていけずに、ひび割れを起こす可能性があります。
施工単価:約3,500~6,000円/㎡
耐用年数:約10年~15年
シート防水とは、シート状の防水材を貼り付けて防水層を成形する工法です。シートの種類は、塩ビシートやゴムシートなどがありますが、現在は耐久性の高い塩ビシートを使用するのが一般的です。
塩ビシート防水の場合は既製品のシートを貼り付けていくため、品質が安定しているというメリットがあります。さらに、大きなシートを使用するので、広い面積でも一度に施工することが可能です。
ただ、複雑な形状にはシート防水は向ていません。シートを施工場所に合うようにカットして、隙間なく貼り付ける必要があるため、複雑な形状だと継ぎ目が多くなり、シート同士の隙間から雨水が浸入するリスクが高くなってしまいます。
施工単価:約5,000~8,000円/㎡
耐用年数:約15年~20年
アスファルト防水とは、アスファルトを含むシートを貼り付けて防水層を成形していく工法です。
防水工法の中で最も歴史のある工法で、実績が豊富にあるのが特徴です。また、耐久性・耐水性に優れており、ビルや大型商業施設などによく採用されています。
デメリットは、作業内容によっては火を使うため、臭いや煙を発することがある点です。アスファルト防水には「熱工法」「トーチ工法」「常温工法(冷工法)」の3種類あり、熱工法の場合はアスファルトを熱で溶かすため、臭いや煙が発生してしまいます。
トーチ工法はアスファルトをバーナーで炙る方法を用いり、臭いや煙が少ない特徴があります。また、常温工法(冷工法)であれば熱や火を付かないので、臭いや煙の心配はありません。
施工方法については、事前に業者と相談しておくことが大切です。
屋上の防水工事は、雨漏りを防ぐためにも非常に重要な工事です。雨漏りが発生すると、躯体の腐食やシロアリ・カビの発生などを引き起こし、耐震性にも大きな影響を与えてしまいます。
防水工事の種類は、大きく分けて「ウレタン防水」「FRP防水」「シート防水」「アスファルト防水」の4つあります。費用や耐用年数などがそれぞれ異なるため、業者と相談をしながら、施工場所に適した工法を選ぶことが大切です。
弊社では豊富な実績を基に、建物の状態やオーナー様のご要望に適した防水工事をご提案しておりますので、大規模修繕をご検討中の場合はぜひご相談ください。私共がサポートさせていただきます。

