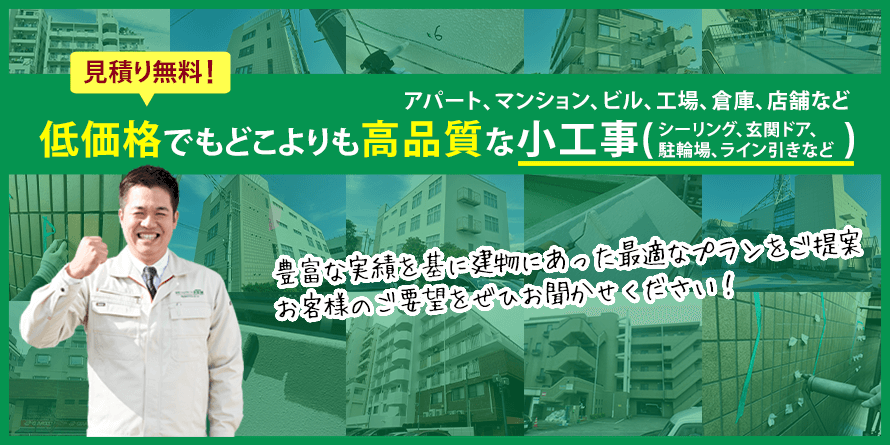
シーリングとは、外壁材の継ぎ目やサッシ周り、屋根と外壁の接合部などに施されているゴム状の部材を指します。
シーリングの役割は、繋ぎ目から雨水が内部に入らないように防ぐことです。万が一、シーリングが適切に施工されていなかったり、劣化を放置していると、目地部分から雨水が浸入して、建材の腐食や雨漏りの発生に繋がってしまいます。
雨漏りは、シロアリやカビの発生、木材の腐朽、鉄部のサビ、耐震性の低下など様々なトラブルに発展し、さらに建物の資産価値が低下する原因にもなります。そのため、定期的にメンテナンスを行い、雨漏りを未然に防ぐことが重要となります。
また、シーリングは美観にも大きく関わり、ひび割れや剥がれが起きていると、建物全体の劣化や汚れを印象づけてしまいます。建物の外観は、入居者の満足度や入居率にも影響するため、綺麗な状態を保つことが大切です。
シーリング材には、主に次の4種類あります。
■ウレタン系
ウレタン系シーリング材は、弾性や密着性に優れている特徴があります。外壁のシーリング補修で使用されることも多いです。
デメリットは、紫外線に弱く、ホコリや汚れが付きやすい点です。そのため、ウレタン系を施工する場合は、シーリングの上から塗装をして保護する必要があります。
■シリコン系
シリコン系シーリング材は、耐水性・耐候性に優れており、主にキッチンや浴室などの水回りで使用されます。
外壁に使用する際は注意が必要です。シリコンオイルが含まれているため、ホコリや汚れが付着しやすいというデメリットがあります。また、シーリングの上から塗装はできません。
■変性シリコン系
変性シリコン系シーリング材は耐候性が高く、目地部分やサッシ周りなど建物のあらゆる場所に使用されています。密着性・柔軟性にも優れており、シーリングの上から塗装することも可能です。
大きなデメリットはありませんが、ウレタン系と比較すると、やや密着性に劣ります。
■ポリサルファイド系
ポリサルファイド系シーリング材は、耐久性・耐候性に優れている特徴があり、コンクリートや石材などに用いられることが多いです。
ただし、柔軟性に劣るため、動きの大きい建物には不向きです。また、ホコリや汚れが付着しやすく、シーリングの上に塗装をすると変色や硬化が起きる可能性があります。
シーリング工事を行う時期は使用しているシーリング材の種類によっても異なりますが、一般的に10年~15年程でメンテナンスが必要となります。また、早い場合は5年程で劣化がみられるようになるケースもあります。
シーリングの劣化が進行すると、ひび割れや剥がれ、シーリングが薄くなってしまう「肉痩せ」などの症状が発生します。
これらの劣化症状は雨水の浸入リスクが高くなるため、早めの対処が重要です。放っておくと、シーリングの下に施された防水シートが劣化し、最終的に建材の腐食や雨漏りに繋がってしまいます。
ブリード現象とは、シーリン材に含まれている可塑剤が表面に溶け出して、塗料や汚れと反応し、黒ずみやべたつきを引き起こす現象のことです。可塑剤には、シーリングに柔軟性を持たせる効果があります。
ブリード現象が起きると美観が低下するだけでなく、塗料の耐久性にも影響を及ぼす可能性があるため、状態が酷い場合は新しいシーリング材に交換する必要があります。
ブリード現象を防ぐ方法として、ノンブリードタイプと呼ばれる可塑剤が入っていないタイプを使用する、もしくはブリード現象を抑えられる下塗り材を使用する方法で対策が可能です。
シーリング工事には「打ち替え」と「打ち増し」の2通りの方法があります。劣化状況や施工場所に適した方法で補修します。
■打ち替え
打ち替えとは、既存のシーリングを撤去してから、新たにシーリング材を打ち直す方法です。劣化が激しく、雨漏りしている場合などは打ち替えを行います。
注意点として、既存のシーリングをカッターで撤去する際に、シーリングの下に施工されている防水シートを切らないように作業することが重要です。防水シートが破損すると雨漏りの原因となってしまいます。
打ち替えの費用は、1mあたり800円~1,200円が相場です。打ち増しと比較するとやや費用は高めになりますが、劣化しているシーリングを一新できるため、耐久性や防水性も向上させることができます。
■打ち増し
打ち増しとは、既存のシーリングの上から、新しいシーリング材を重ねて充填する方法です。劣化が少ない場合は打ち増しを行います。
打ち増しの費用は、1mあたり500円~900円が相場です。できるだけ費用を抑えたいという場合は、打ち増しで対応できる状態なのかを業者に聞いてみるのもいいでしょう。
玄関ドアの改修工事を行う目的は次の通りです。
■美観の向上
玄関ドアは建物の顔とも言えるため、ドアの劣化やデザインは美観にも大きく影響します。
美観が向上すれば、入居者の満足度も向上して退去率を抑えられたり、入居率アップにも良い効果を与えることができるでしょう。
■防犯性の向上
防犯性に特化した玄関ドアも多く存在します。例えば、鍵穴が見えないハンドルやピッキングに強い鍵、ガラス破りに対応しているタイプなど様々なものがあります。
また、スマートフォンやカードなどで施錠をするキーレスの鍵に変更することもできるため、防犯性と併せて利便性の向上も期待できます。
■断熱性の付加
玄関ドアは熱の出入りが多い場所ですので、快適な室内環境を維持するためには、玄関ドアの断熱機能が重要なポイントとなります。
断熱性が向上することにより、夏場は涼しく、冬場は温かい室内を実現でき、エアコンや暖房費の削減にも繋がります。さらに、結露の発生を防止できる効果もあり、カビやダニの繁殖を抑えて衛生的な生活環境を作ることができます。
■木製
木製のドアは、木の温かさを感じられる自然な風合いが魅力的な素材です。
木目の見え方や塗装方法などによって雰囲気も変わり、オリジナリティのあるデザイン性の高いドアにすることができます。また、加工がしやすく、断熱性が高いというメリットもあります。
ただ、自然素材であるがゆえに、紫外線や雨風の影響で劣化しやすいデメリットもあるため、耐久性・防水性を維持するためにも定期的なメンテナンスは欠かせません。
■アルミ製
現在、玄関ドアの主流となっているのがアルミ製です。軽量で加工がしやすい特徴があり、さらに耐久性が高く、比較的安価な点もメリットとして挙げられます。
アルミ製と聞くと、シンプルでデザイン性に劣るイメージがあるかもしれませんが、現在は多くのメーカーからアルミ製のドアが販売されており、デザインのバリエーションも豊富に揃っています。
デメリットは、断熱性が低いという点です。アルミは熱伝導率が高いため、夏場は室内に外の熱気が伝わり、反対に冬場は厳しい寒さを感じる玄関となってしまいます。
対策として、断熱材を含むアルミ製ドアを使用するのがオススメです。
■スチール製
スチール製もアルミ製と同様、比較的安価で加工がしやすく、さらにアルミ製と比べて非常に頑丈で、耐久性や防犯性に優れている特徴があります。
防火性や遮音性も高いため、集合住宅やホテルなどの玄関ドアによく使用されています。デザインはシンプルなものが多く、スタイリッシュで洗練された雰囲気を作ることが可能です。
デメリットは、やはり金属製なので断熱性に劣り、デザインのバリエーションも少ない点です。また、重量があるため、開閉時に負担を感じることもあるかもしれません。
■ステンレス製
ステンレス製のドアはサビにくく、耐久性に優れているため、潮風や紫外線の影響を受けやすい沿岸地域でも使用できるのが大きな特徴です。
ただ、デザインはシンプルなものが多く、バリエーションは少なめです。沿岸地域以外で、ステンレス製ドアを選ぶメリットは少ないと言えます。
■建付けが悪い
ドアの開閉がスムーズにいかない、ドア枠にこすれて異音がするといった不具合はよくあります。原因は様々ですが、経年劣化や地震の揺れなどによる建物自体の歪みが挙げられます。
修理で直る場合は、1万円~3万円程が相場です。ただし、部分的な修理で改善しない場合は、ドア本体のリフォームが必要となります。
■ドアクローザーの不具合
ドアクローザーとは、玄関ドアの上部に取り付けられているボックス上の部品です。ドアクローザーが劣化すると自動で開閉する機能が正常に働かず、急にドアが閉まったり、最後まで閉まりきらないというような不具合が生じます。
また、ドアの動きが不規則になると、開閉時に指を挟めてしまうなどの事故に繋がる可能性も高くなるため注意が必要です。
修理費用は、ドアクローザーのネジを調整だけで改善する場合は1万円程度で済み、ドアクローザー本体を交換する際は2万円~5万円が相場となります。
■ドアノブ・ドアハンドルの不具合
毎日ドアを開け閉めしていると部品が摩耗したり、ドアノブ・ドアハンドルに緩みやがたつきが生じることがあります。ドアノブ・ドアハンドルの不具合を放置していると動きが悪くなり、開閉がスムーズにできなくなるため修理が必要です。
修理にかかる費用は、不具合の原因やドアノブ・ドアハンドルの種類によって異なりますが、部分的な修理であれば1万円程度、交換を行う場合は2万円~8万円が相場となります。
■ゴムパッキンの劣化
玄関ドアとドア枠の隙間には、気密性を維持する目的としてゴムパッキンが施工されています。ゴムパッキンは開閉を繰り返すことで摩耗していき、さらに紫外線の影響を受けて弾力を失い、やがてひび割れを引き起こすケースもあります。
ゴムパッキンの劣化や割れは、風や虫が内部に入り込む原因となるため、室内環境を整えるためにも早めの対処が必要となります。
ゴムパッキンの修理・交換費用は1万円~3万円程が相場です。
■鍵・シリンダーの故障
シリンダーとは、鍵を挿し込む円筒状の部品のことを指します。
鍵が抜きにくくなったり、スムーズに回らなくなった場合は、鍵やシリンダーが年月の経過とともに摩耗していたり、シリンダーに砂やホコリなどが詰まっている可能性があります。
鍵・シリンダーの不具合は防犯に大きく関わる部分なので、早めに修理することが大切です。その際、自分で直そうとすると状況が悪化してドアが開かなくなる可能性もあるため、必ず専門業者に依頼するようにしましょう。
修理費用は原因によって異なりますが、1万円~5万円程が相場となります。
■へこみ・傷
ドアのへこみ・傷は大きなトラブルに発展する心配はありませんが、美観を損なったり、サビの発生を招く可能性があります。へこみ・傷が起きる原因としては、人為的なものや強風時に飛来物が当たった等が考えられます。
へこみ・傷の修理費用は施工範囲によっても異なりますが、2万円~7万円が相場です。劣化部分をパテで埋め、その上から塗装をして仕上げます。
■玄関ドアの交換
ドア枠はそのまま残し、玄関ドアのみ新しいものに交換します。注意点として、玄関ドアのみ交換する場合は、既存のドア枠に合うサイズを選ぶ必要があります。
また、ドア枠の傷みが激しいと新しい玄関ドアとの差が目立ってしまう可能性もあるため、もし劣化の差が気になる場合はドア枠の塗装も併せて行うといいでしょう。
玄関ドアの交換費用は、新たに設置するドアの種類や製品によって異なりますが、15万円~30万円程度が相場となります。ドア枠を撤去せずに再利用するため、費用を抑えてドアのリフォームが可能です。
■玄関ドア・ドア枠の交換
ドア枠に割れや歪みが生じていたり、ドア自体のサイズを変更したいという場合は、玄関ドアとドア枠どちらも新しいものに交換します。
ドアをフルリフォームできるため、製品も自由に選ぶことができますが、壁を壊す必要があるので費用や工期がかかります。できるだけ費用や工期を抑えたいという方は、既存のドアと同じサイズのものを選ぶといいでしょう。
玄関ドア・ドア枠の交換費用は、新たに設置するドアの種類によっても異なりますが、40万円~100万円程度が相場です。
■カバー工法
カバー工法とは、既存のドア枠の上から新しいドア枠を被せ、どのドア枠に併せて新規の玄関ドアを取り付ける方法です。玄関ドアのリフォームとして一般的によく用いられています。
ただ、ドア枠が2重構造になるため、ドアのサイズが数センチ狭くなったり、立ち上がり部分に段差ができてしまうケースもあるため、あらかじめ開口部の広さや段差の高さについても確認しておくことが大切です。
カバー工法にかかる費用は設置する製品によっても異なりますが、20万円~40万円程が相場となります。
■塗装
塗装の剥がれやサビなどが発生している場合は、塗り替えを行うことで美観が回復します。ドア自体の破損等が無く、見た目を綺麗にしたいという方にオススメです。
サビが発生している場合はサビをしっかりと除去してから塗装をすることで、サビの再発を防ぐことができます。また木製ドアの場合は、木目を残すのかを考えて塗料を選ぶことが大切です。
玄関ドアの塗装にかかる費用は、塗料の種類やドアの素材などによって異なりますが、5万円~20万円程が相場です。
■シート(フィルム)を貼る
塗装を行わずに、玄関ドア専用のシート(フィルム)を貼って綺麗に仕上げる方法もあります。費用を抑えて簡単にリフォームしたい方にオススメです。
シート(フィルム)の種類も多く、豊富なデザインや色の中から好みのものを選ぶことができます。ただし、製品によって耐久性た適した素材が変わってくるため、性能についてもしっかりと確認しておく必要があります。
費用は使用する製品やサイズなどによっても異なりますが、7万円~15万円程が相場となります。
イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。イメージ確認用のサンプル文言になります。
駐輪場の改修工事を行う目的は次の通りです。
■入居者の満足度向上
入居者にとって駐輪場は日常的に使用する場所です。駐輪ラックや屋根をしっかりとメンテナンスし、駐輪場が使いやすく綺麗に整っていれば、入居者の満足度アップに繋がります。
反対に、駐輪場に不備がると入居者が不便を感じるだけでなく、自転車同士がぶつかり合って傷がついたり、雨漏りによって自転車の水濡れやサビの発生などを引き起こすなど、不満やクレームに繋がってしまいます。
駐輪場は多くの入居者が出入りスペースでもあるので、入居者同士のトラブルを防ぐためにも、きちんと整備をして正しい位置に自転車を停められるように対策することが大切です。
■美観の向上
駐輪ラックや屋根の破損、サビの発生、地面のラインが消えている等の劣化が見られる場合は、駐輪場のメンテナンスを行うことで美観の向上に繋がります。
さらに、駐輪場を整備することで利便性が高まったり、停められる台数を増やすこともできるため、駐輪場以外のスペースに自転車を放置されるケースが減り、敷地内全体の美観もアップします。
また、駐輪場の綺麗さや放置自転車の有無は、入居率にも大きく影響します。
自転車が乱雑に置かれていると、「ここに住んでる人はだらしない人が多いのかな?」「トラブルがあった時にきちんと対応してくれるだろうか」など、入居者やオーナー様に対して不信感を抱かれる原因となってしまいます。
■安全確保
駐輪ラックや屋根の破損や乱雑している自転車を放置していると、設備が倒壊したり、自転車が倒れてきて、利用者や自転車を傷つけてしまう恐れがあります。
大きなケガを負ってしまったり、思いもよらないトラブルに発展する可能性もあるため、安全性を確保するうえでも駐輪場の改修工事はとても大切です。
■屋根の設置
雨によって自転車が濡れてしまうと、自転車の劣化が進んだり、入居者の不満が増幅する原因となるため、駐輪スペースには屋根を設置するのが望ましいです。もし屋根や支柱に割れ・破損が見られる場合は、新しいものに交換しましょう。
屋根の新設・交換費用は5万円~40万円程が相場です。使用する材質や駐輪スペースの面積によって変動します。
■床面の補修
床面のコンクリートやアスファルトに割れや段差ができている場合は、モルタルなどを埋めて補修します。また、塗装をして耐久性を高めたり、滑りにくい床にすることも可能です。
床面の補修にかかる費用は工事内容や施工面積で異なりますが、部分的なひび割れ補修であれば数千円~、塗装を行う場合は使用する塗料によって大きく変動し、㎡あたり4,000円~20,000円程が相場です。
■ライン引き
駐輪スペースを区切るためのラインが消えていたり、元からラインを引いていない場合は、ライン引きを行うことで簡単に駐輪スペースを整備できます。番号などを割り当てて、駐車場所を固定することも可能です。
ライン引きの費用は、施工面積や番号の振り分けの有無などによって変動し、6万円~が相場となります。
■駐輪ラックの新設・交換
駐輪ラックを設置することで駐輪場が綺麗に整い、利便性も向上します。ラックの破損や歪みが起きている場合は、事故やトラブルに発展する前に修理や交換を行いましょう。
ラックの種類にもいくつかあり、2段式ラックなどを導入して収容できる台数を増やすことも可能です。また、入居者ごとに使用するラックを決めることで、放置自転車や入居者同士のトラブルを防止できるメリットもあります。
駐輪ラックの設置費用は、ラックの種類や台数などによって大きく異なりますが、1台あたり4万円~が相場となります。
駐輪ラックは、大きく分けて「平面式ラック」と「2段式ラック」の2種類あります。
■平面式ラック
平面式ラックは、横並びに自転車を収容できるタイプのラックです。
形状も様々なものがあり、例えば「平置きラック」は最もシンプルで、自転車を地面に直接置き、前輪のみ収容します。マンションやビルをはじめ、スーパーなど街中のどこでも使用されています。
その他にも左右にスライドさせて自転車を出し入れする「スライド式平置きラック」や、ラックに傾斜を付けて自転車のハンドルがぶつかり合わないように工夫されているもの、前後から自転車を収容できるタイプなどがあります。
■2段式ラック
2段式ラックは、名前の通り自転車を上下2段で収容できるタイプです。平面式ラックと比べて収容できる台数が多く、狭いスペースでも収容力を高められるメリットがあります。
ただ、自転車を収容する際にラックを手前に引いて降ろし、自転車を斜めにして持ち上げる必要があるため、弱い高齢者や子供では力が足りずに扱いにくい可能性があります。最悪の場合は事故に繋がる恐れもあるため、注意が必要です。
入居者に高齢者や子供が多い場合は「垂直2段式ラック」がオススメです。通常の2段式ラックとは違い、小さな力でラックを操作することが可能で、自転車を斜めに持ち上げる必要もありません。
まずは入居者にアンケートを行い、駐輪場の使い勝手や自転車の台数、種類、将来の所有予定を聞いてみるようにしましょう。これらの情報を把握することで、必要な駐輪スペースやラックの収容台数がわかります。
その際、重要なのはチャイルドシートや電動アシスト自転車、原付・バイクの有無も確認することです。
チャイルドシート付き自転車や電動アシスト自転車は、スタンダードな自転車よりも横幅や高さ、重さがあります。
そのため、ラックの間隔や屋根の高さを配慮しないと、きちんと自転車を止めることができなかったり、自転車の出し入れが困難になってしまう可能性があります。
また、原付やバイクを駐輪場に停めるように定めている場合は、これらの乗り物も収容」できるスペースやラックを設置しなければなりません。
入居者のニーズに合わせた駐輪場を意識することで、より快適で使いやすい環境になり、美観の向上や満足度の向上などプラスの効果を得ることができるでしょう。
シーリングによる防水機能を維持するためには、10年~15年程ごとを目安にメンテナンスを行うことが重要です。立地条件や使用している材料によっては、5年程で劣化がみられるようになるケースもあります。
玄関ドアは、建物の美観はもちろんのこと、断熱性や防犯性も左右する重要な部分です。定期的な点検や修理を怠っていると、室内に熱気や雨風が入ってきたり、犯罪被害に遭うリスクが高まってしまうため、注意が必要です。
各部屋のドアをフルリフォームするのは大変な作業かと思いますが、カバー工法やシート(フィルム)を使用するなど様々な方法があるため、劣化状態や予算に合ったメンテナンスが可能です。
また、駐輪場も入居者とって重要な設備のひとつです。しかし、屋外に設置されていることも多く、劣化の進行が早かったり、メンテナンスが行き届かない場所でもあります。
大規模修繕の際にシーリングや駐輪場などの修理・改修工事も一緒に行うことで美観や耐久性も向上し、入居者の満足度や入居率アップにも繋がります。
敷地内の劣化や故障など少しでも気になる点がある場合は、お気軽に弊社までお問い合わせください。オーナー様のご要望に適したプランをご提案させていただきます。

